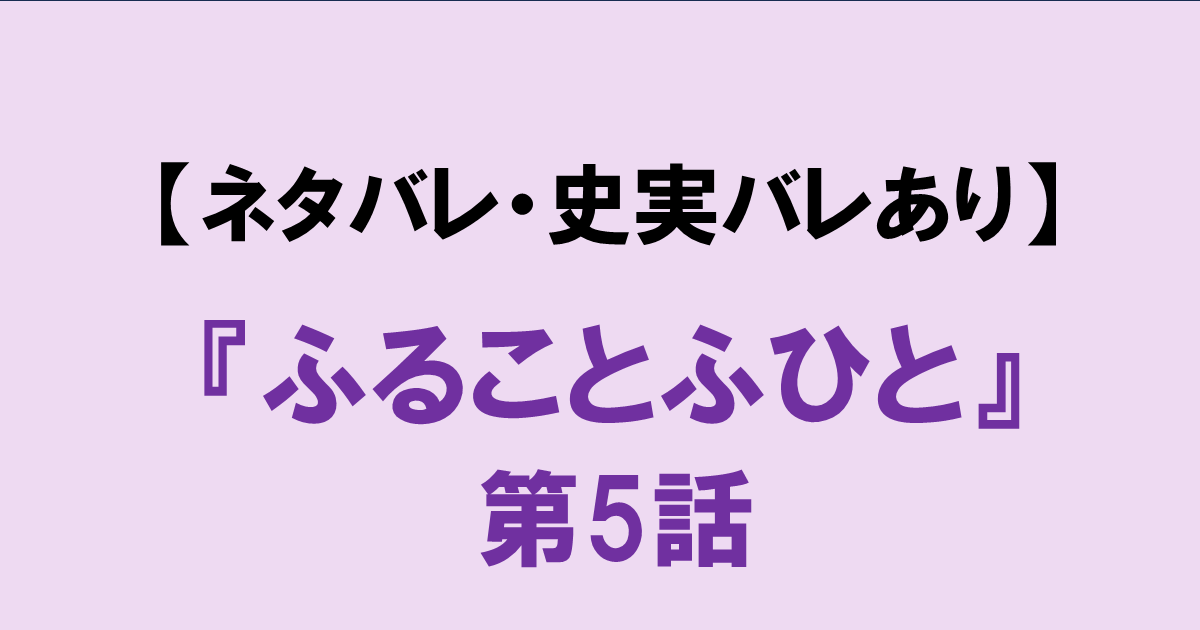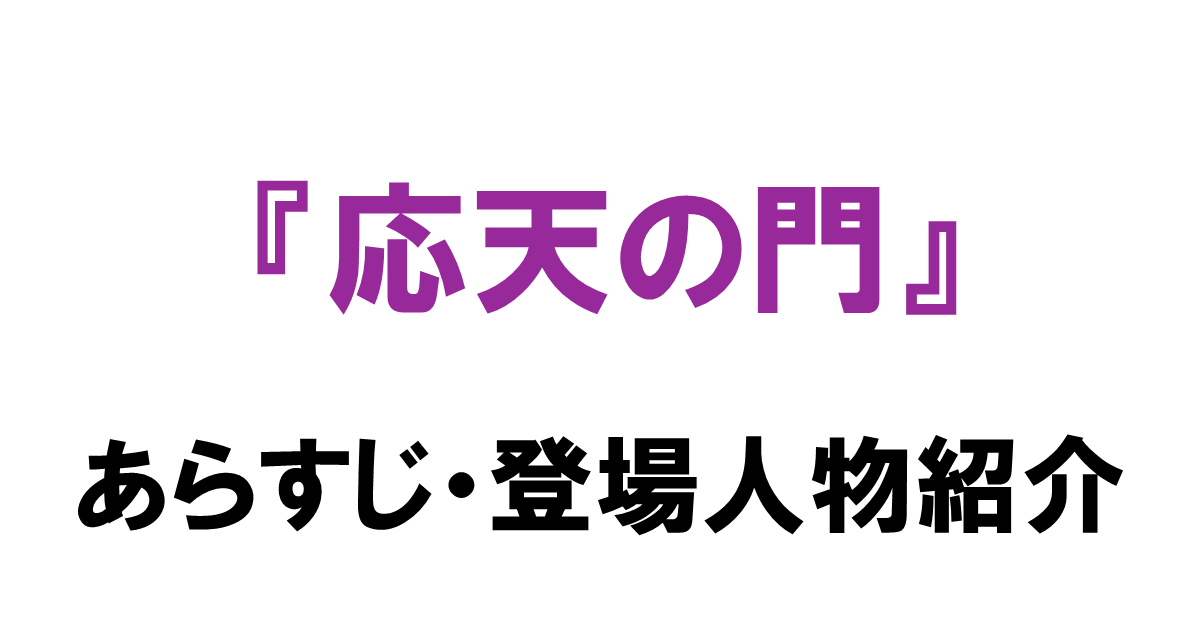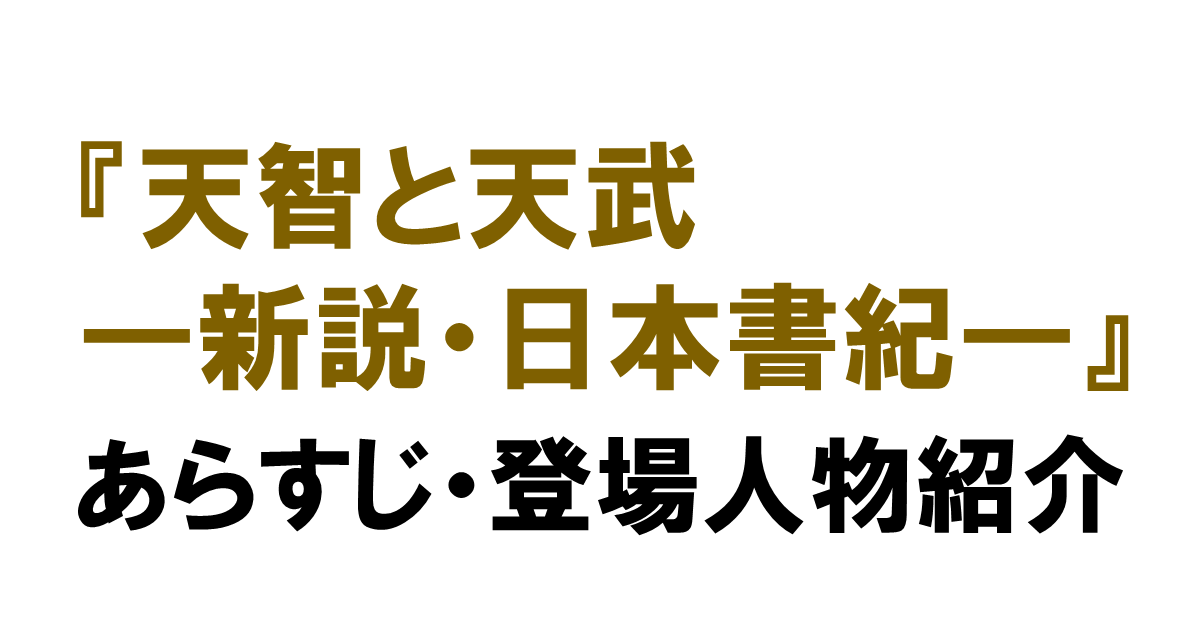『ふることふひと』第5話をご紹介します。
今回の舞台は、史の師であり養父のいる山科です。
壬申の乱の時にあった出来事。安萬侶が文字を大切にする理由。そして、史自身に関する重大な秘密が明らかになります。
本編紹介
山科へ
山科に同行することになった安萬侶は、お付きの者をつけず、一人でやってきます。
多(おお)の者がぞろぞろ来たら田邊も迷惑だろうとの、安萬侶の気遣いでした。
百枝は安萬侶の事を多少警戒しているようです。
かつてあった天下を二分する戦で、多と田邊は敵対する陣営に属していたのでした。
当時は敵同士であった筈の私達は
今こうして共に馬を並べ
山科へ向かっている
壬申の乱勃発時
ここで回想が入ります。
672年6月25日。女子の格好をした史は、侍女(まかたち)たちと遊んでいました。
史は女装に不満です。この格好で過ごし始めて、半年が経っていました。
そこに田邊史大隅の息子・田邊小隅が、大津から知らせを持ってきます。
大皇弟(おおすめいろど)が吉野を出た、戦が始まると。
大皇弟・大海人皇子は出家して吉野に隠遁し、後継者争いから離脱する意志を示していました。
しかし大津の人々は額面通りには受け取りませんでした。『虎に翼をつけて放つ様なものだ』と噂します。
大皇弟は実績も人脈もあり、母の身分が低い皇太子(ひつぎのみこ)よりも次期大王に相応しいと考える者も多かったのです。
史の父である鎌足が存命であれば大皇弟を生かして都から出す事はなかったと、大隅は語ります。
そして起こった内戦で、皇太子は自害し、大皇弟が勝利したのでした。
朝廷軍として参戦していた大隅の息子・小隅は行方知れずのまま、六年が経とうとしていました。
史の女装は半年前から。
今の大王・当時の大海人皇子が出家して都を出たのが671年10月17日で約8ヶ月前なので、大隅はその頃から内乱を予測して史を逃がす準備をしていたんですね。
「皇太子」は先皇(さきのみかど。大海人皇子の兄である、天智天皇)の息子である大友皇子ですね。作中ではまだ名前が出ていません。
大友皇子を皇太子と記すのは『懐風藻』など。『日本書紀』では大友皇子立太子の記事はなく、大海人皇子が「東宮」と呼ばれています。
ところで、小隅が行方知れずになって六年が経とうとしているということは、現在は677年か678年ごろ。659年生まれの史は満18歳か19歳くらい。女装して良いか微妙な年齢ですね。
さて、ここで壬申の乱の勝者、史に史書の編纂を命じた大海人大王(天武天皇)を見ておきましょう。
天武天皇(631?~686)在位673~686。
舒明天皇の子、天智天皇の弟で大海人皇子という。
壬申の乱後、飛鳥浄御原宮で即位。皇族を重用して天皇政治を強化し、八色の姓を制定。
新冠位48階を定め、立札の礼法も整える。
飛鳥浄御原宮律令や国史の編纂にも着手。引用:日本史B用語集 改訂版(山川出版社)
掲載教科書は当然11冊中11冊。多くの実績のある力のある天皇です。
本作に関係の深い部分は壬申の乱と、そして「国史の編纂にも着手」ですね。
小隅の最期
史たちは田邊史大隅の屋敷に到着します。
馬から降りると同時に盛大にコケる安萬侶。転ぶのは慣れているとのこと。
そして大隅に対面。安萬侶は「安八磨評(あはちまのこおり)の湯沐令(ゆのうながし)多臣品治が子 安萬侶と申します」と自己紹介します。
安八磨評は三野国(みののくに)。大王は吉野から脱出する前に近淡海(おうみ)と三野の国境である不破関(ふわのせき)を塞ぐように安萬侶の父に命じました。これによって近淡海朝廷は東国からの徴兵ができず、それが敗因の一つとなっています。
その後安萬侶の父は三野を出て莿萩野(たらの)に駐屯。
小隅の方は、その前方の倉歴(くらふ)の吉野軍を壊滅させ、翌日莿萩野を攻撃します。
しかし安萬侶の父はこれを撃退、さらに追撃します。
敗走する小隅は途中で崖下に滑落、亡くなってしまいます。
ことの顛末を聞いた大隅は安萬侶に礼を言い、これでようやく自分の戦も終わると言って笑います。
生きてはいないだろうと思いながら、どこかで息子の帰りを待っていた気持ちに、やっと区切りがつけられたようです。
その姿を見て、安萬侶は「敗者の歴史を入れるべきではない」と言ったことに、思うところがあった様子です。
これでようやく…
ようやく私の戦も終わります
聞き慣れない地名や用語が出てきたので調べてみました。だいたいwikipedia情報です。
安八磨評は今の岐阜県の地名。岐阜県の南西部に位置し、現在は安八郡(あんぱちぐん)と呼ばれています。
美濃国は7世紀には「三野国」と記されていたようです。
そして湯沐令は官職の名前。皇族の領地である湯沐邑(ゆのむら)を管理するのが役目でした。
不破関は安八磨評よりさらに西。日本書紀では「急(すみやか)に不破道を塞(ふせ)け」と書いてあります。
不破関が鈴鹿関、愛発関とあわせて「三関(さんげん)」として整備されたのは壬申の乱の後のようですね。
莿萩野は伊賀国(現在の三重県西部)の北部の地。倉歴は現在の滋賀県甲賀市と三重県伊賀市の間に位置する峠です。
安萬侶の道
史は部屋の外に出ていた安萬侶に声をかけます。
安萬侶は木簡を持っており、和歌を詠んでいたようでした。
見せるのは絶対嫌だと木簡をしまう安萬侶は、月を見ていたと話します。小隅が最期に見た月はどんな形をしていたのだろうかと。
史も安萬侶も、壬申の乱の時にはまだ年少で、戦に出たことはありません。
安萬侶と戦場で出会うことがなくて良かったという史。
安萬侶は体格差があるから史に負けるといいます。
安萬侶は小柄でした。よく転ぶのも服が大きすぎ裾を踏んでしまうためのようです。
武人の子にしては小柄すぎて、多(おお)の人間は安萬侶に期待していない。だから氏名(うじな)の漢字も『多』ではなく『太』に変えた。武の道を諦めて文官として堂々と生きていくためには文字の持つ力と知識が必要だと安萬侶は言います。
安萬侶が和文を漢字を使って書き記す術を身につけたのも、そういう思いがあったからなのでした。
安萬侶は自分の才を見出してくれたと、史に礼を述べます。
木簡を見られたのは不本意だったが
最初に俺の才を見出してくれたのは史殿だ
その点に関しては感謝している
小隅が最期に見た月の形に思いをはせる安萬侶、夜襲だから月をみる余裕などなかったという史。
史はドライで、安萬侶の方が繊細な感覚を持っていそうです。
ところで月の形ですが、この頃は太陰暦だから、日付がわかれば月の形がわかりますよね。
これは安萬侶自身が「翌六日」と言っています。
なので上弦の月まであと少しという形だったと思われます。
小隅は夜襲を仕掛けた側ですから、行動前に月を見ていた可能性はありますよね。
もしくは滑落した後しばらく意識があって、月が目に入ったかもしれません。
出生の秘密
安萬侶と話していた史に、百枝が声をかけます。大隅が大事な話があると呼んでいると。
史は以前出した書簡の件だと思い、師のもとに向かいます。
大隅は、命の尽きる前にどうしても伝えなければならないことがあると史に言います。
書簡の件はもう良いと史。八尺鏡の件は藤原の都合の良いように教えられたかと疑ったが、鏡は光を受けなければ意味がないと気づいたと説明します。
それに対し、大隅は本当に鏡は大御神以外は映さなかったと思うかと問います。火の神がいたかもしれない、月の光があったかもしれない。
それはさすがに詭弁だ、可能性の話まで持ち出したら如何様にでも読み取れてしまうと反論する史に、この世の実(まこと)とは語られぬ行間のように曖昧なものだと大隅は語ります。
史書の改竄を心配する史に、大隅は史書「は」改竄していないと答えます。
その言葉に引っかかりを覚える史。
大隅は史に向き直り、重大な事実を伝えます。
近淡海朝廷は滅んでいない。先皇(さきのみかど/天智天皇)が内大臣(うちつおおおみ/中臣鎌足)にたくし、密かに匿われた皇子(みこ)がいる。
その子は本来の名も知らず、藤原家の子として育てられた。時がきたら大王(おおきみ)より賜った名をその子にお返しする。それが史の父の遺言。
史の名前は史部(ふひとべ)の姓(かばね)から名づけられたものではない。実(まこと)の意味は……
実の意味は
『等しく比(なら)ぶ者不(な)き』お方…不比等
先皇(さきのみかど)が遺された藤原皇子(ふじわらのみこ)様でございます
重大な事実の発覚です。
藤原不比等が天智天皇の落胤だという説は、『公卿補任』『大鏡』『帝王編年記』『尊卑分脈』と、複数の文献に記載されているようです。
大王の子であり藤原皇子。これはどうとらえれば良いのでしょうか。
藤原鎌足と血のつながりがないのであれば、実は藤原とは関係のない人間であるという解釈もできそうですが、藤原皇子というからにはそういうことではないようです。
鎌足に託され藤原の子として育てられたからには、藤原とは無関係ではない。
でも血は天智天皇のものだから、近淡海朝廷は滅んでいない。だけど天智天皇の子は他にもいますよね。
藤原と大王の両方の力を持つ、比類ない者、ということでしょうか。
後に藤原の娘が将来の天皇を産んだように、「藤原家出身の天皇」になり得る者という意味合いもあるのかもしれません。
何にせよ、近淡海朝廷の重臣であった鎌足の子でもある史(不比等)は、他の皇子よりも近淡海朝廷復興にふさわしい人物なのでしょう。
それに、今回の話の翌年か翌々年には、吉野の盟約が行われます。
そこでは天武天皇は、天智天皇の子も自分の子のように扱っています。
言い方は悪いですが、天智天皇の他の皇子は天武天皇に取り込まれ済みということなのかもしれません。
ところでまた脱線するのですが、八尺鏡は石屋戸から姿を見せた天照大御神の光を受けて初めて輝くという史の考えは、やはりちょっと無理がある気がします。
というのは、真っ暗で何も見えなかったら、天宇受賣命(あめのうずめのみこと)の舞も見えないので。
まとめ
『ふることふひと』第伍話を紹介しました。
今回は古事記の編纂はお休み。壬申の乱の爪痕、安萬侶の文字への想い、そして史の出生の秘密が明らかになりました。史(不比等)がそれをどう受け止め、どういう道を選ぶのか。今後に注目です。
関連書籍紹介
一般向けに出版された、高校の日本史教科書です。
漫画で何巻にも渡って描かれることも、教科書では一瞬なんですよね。
↓クリックして頂けると嬉しいです。
にほんブログ村